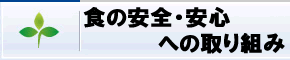
当社では創業以来、常に「安全・安心・鮮度・旬・健康」を第一に考えた事業展開を行って参りました。食を通じて「人類の健康と心の豊かさに奉仕する」という理念を実現するためには当然のことだと考えているからです。
- 大庄基準

大庄基準とは?
庄やグループのお店で安心してお食事を楽しんでいただくために独自の基準を設けています。

農産物の栽培に関する大庄基準
農薬を可能な限り使わない取り組みを生産農家とともに実現していきます。

農産物の残留農薬に関する大庄基準
健康への影響と環境への負荷軽減を考え、国の基準よりもさらに厳しい残留農薬基準を設けています。

畜産物・水産物に関する大庄基準
生産者に飼養履歴の整備や国の飼料の有害物質の指導基準の順守をお願いし、安全管理に努めた生産物の確保を進めていきます。

栽培(飼養)履歴の記帳及びトレーサビリティの確保に関する大庄基準
生産者との密接な関係を築き、栽培の履歴から細かく把握する体制を構築し、トレーサビリティの確保を推進しています。

食品添加物に関する大庄基準
わが国で使用が認められている場合でも、健康を損なう疑いのある食品添加物を使用した加工食品は、庄やグループとして取り扱わないこととしています。

品質確保・管理(微生物)に関する大庄基準
厚生労働省や地方自治体の基準に基づく細菌検査を実施しています。

加工品の品質に関する大庄基準
安全・品質確保のために、加工業者からの原材料情報の提出を徹底しています。

放射能汚染の安全確認に関する大庄基準
庄やグループとして、安全を図るための基準を設け、万全な仕組みで安全・安心なお料理をお客様にご提供します。

安全性に懸念のある国の品目に関する大庄基準
食品安全に関する国内外の情勢の中で安全性に問題が生じた場合には、安全確認とともに、お客様や消費者の理解が得られるまでの期間、該当する国の品目を使用しません。

遺伝子組み換え作物(GMO)の使用及びアレルギー表示に関する大庄基準
遺伝子組み換え作物、アレルギー表示への対応にも取り組んでいます。

付則)お客様への情報提供に関する大庄基準
お客様の求める情報をいつでも提供できる環境づくりに取り組んでいます。

大庄基準の遵守
食材の生産、加工、流通等に関わる関係者に、基準の周知徹底を行い、大庄基準を遵守します。
- 検査研究施設

大庄総合化学新潟研究所
お店で使用する青果物や、魚・お米などの食材全般について、独自の使用基準として「大庄基準」を定め、研究所で農薬残留物や重金属・食品添加物、栽培履歴などの安全確認を行い。お客様が安心して飲食をしていただけるように年間を通じて食材を厳しく検証しています。
-

食品衛生研究所
食の安全・安心確保のプロ集団として、ご提供するお料理や店舗環境の衛生管理、および従業員の衛生教育など、外食産業には欠かせない重要な業務を担っています。











