
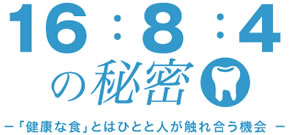
人間の歯の数は28本(親知らずを含めると32本)が標準です。この「歯」の構成を見ると、私たち人間にどのような食生活に適しているかがわかる、という考え方があります。
人間の歯は、臼歯(穀物や豆をすりつぶす歯)が16本、切歯(野菜などを噛むための歯)が8本、犬歯(肉や魚を噛み切るための歯)が4本で構成されています。この構成比と同じ割合で食事を取ると、とてもバランスの良い食生活になると言われています。消化器への入り口である歯が、人間の理想的な食事を表しているとは驚きです。
よく噛んで食べる、ゆっくり食べるなどは昔から良く言われていますが、そのためには食事を楽しむことが大切です。家族や友だちとの会話を楽しみながら食事をする機会を増やせば、おのずと食事の時間も長くなり、ゆっくり食べるようになるでしょう。
いまは「個食」の時代とも言われています。個食とは、ひとりで食事をすることです。家族との縁、友だちとの縁が薄れてきていることを象徴しています。ゆっくり食べるために環境を見直すことは、健康な体をつくるだけでなく、人々が触れ合う機会を増やし、良い人間教育の場としての期待がもてます。
「食べる」とはなにか、皆さんもぜひ考えてみてください。次回は私たち庄やグループが皆さまに提供したいと考える「健康な食」への取り組みです。